2020年から小学校でのプログラミング教育が必修となります。しかしプログラミングって難しそう、なにをするの?といった声も聞かれます。ここでは簡単に子どものプログラミング教育についてのお話をしたいと思います。
プログラミング教育のねらい
文部科学省が提示しているプログラミング教育のねらいは以下の通りです。
- 「プログラミング的思考」を育む
- プログラムの働きやよさ情報社会がコンピュータをはじめとする情報技術によって支えられていることなどに気付く
- 身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコンピュータなどを上手に活用してよりよい社会を築いていく態度などを育む
- 各教科などの内容を指導する中で実施する場合には、教科等での学びをより確実なものとする
プログラムを作成する際、物事を順序立てて理解する必要があります。たとえば、「机の上のりんごを取る動作」を考えてみます。
このようにりんご1つ取る動作でも、その過程をプログラムで実行しようとした場合、動作を一つ一つ分解し、順序立てて考える必要があります。
以前に比べ、スマホやパソコンが普及したことで、今の子ども達には、プログラムがより身近になってきました。生活の至るところにコンピュータ技術が使用されていますが、家庭によっては、まだまだコンピュータと無縁の生活を送っていると思っている方も多くいるのではないでしょうか。今後より一層パソコンをはじめ、コンピュータ技術に頼る場面が増えてくることが予想されます。学校教育の一貫としてプログラミング学習が行われることで、プログラムがより身近になり、情報を扱う際の格差も是正されることを期待したいです。
また、現在働き方改革としきりに言われていますが、まだまだプログラムで簡単にできることを数時間もかけて手作業で行っていることが多いです。小さい頃から、プログラミング技術を身につけることで、誰しもが簡単にプログラムを組めるようになり、仕事の効率を上げることができるのではないでしょうか。
プログラム的な思考は、実はとても身近です。既存の教科でも応用できます。プログラミング教育の狙いとしては、この点も考慮してやっていこうということですね。
まとめ
2020年から小学校でのプログラミング教育が必修となりますが、要は物事を順序立てて考えることを学ぶことではないかと思います。無意識に既に出来ている子もたくさんいると思いますが、今後それを教科として学んでいこうということではないでしょうか。
ある目標を決めて、それをするにはどうすればいいのかを試行錯誤しながら、目標に到達できれば、小学生のプログラミング教育としては十分ではないでしょうか。
プログラミング教育と同時にインターネット上での著作権等の扱いやネチケットについても、これからの情報社会ではとても重要です。このプログラミングの必修化と同時により一層力をいれてもらいたいなと感じます。
また、新型コロナウイルスの影響で、今後パソコンを使ってのリモート授業等も普及する可能性があります。より一層IT技術に対する依存度は上がる可能性が高いです。子どものころから苦手意識を持たず、楽しんで学んでもらえばと思います。

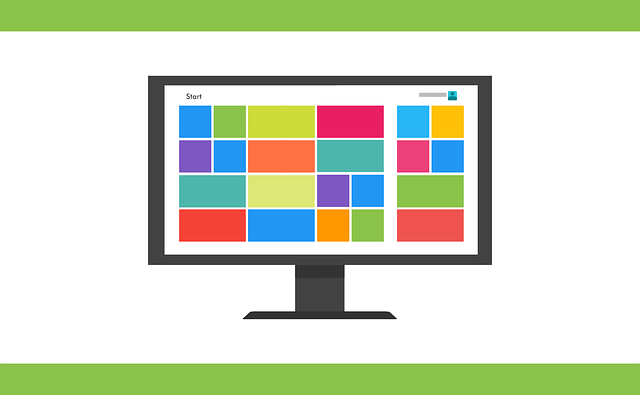


コメント